
法人や個人事業主の方が、事業に使うための融資です。
融資事務の流れ
①受付
⬇ 借入申込書の記入、必要書類の徴求
②審査
⬇ 資格・信用調査、稟議書作成、融資実行の可否
③実行
⬇ 意思確認、必要書類の徴求、融資金の授受、書類の保管
④管理
⬇ 融資先の状況の継続的な把握
⑤回収
融資先から融資金の返済を受ける
銀行にとって融資は、回収する(全部返してもらう)までが1つの流れです。
審査10項目
①業態
・ 何を作っているのか?
・ 何を売っているのか?
・ 誰に売っているのか?
②業績・業況
・ 売上や利益はどうなのか?
・ 前期と比べて当期はどうか?
③財務・資金状態
・ お金は足りているのか?
・ 不測の事態に備えはあるのか?
④資金需要の発生原因
・ なんでお金が必要になったのか?
⑤資金使途
・ お金を何に使うのか?
・ 使い道は妥当なのか?
⑥返済財源・返済能力
・ 借りたお金を返せるだけの収益はあるのか?
⑦保全・信用
・ 担保はあるのか?
・ 信用貸の場合、根拠は妥当なのか?
⑧融資方法・条件
・ 資金需要・資金使途・金利設定の妥当性は?
⑨融資効果
・ この融資の取り組みによってどんな効果があるか?
・ 今後も安定した取引が見込めるか?
⑩取組方針
・ 問題点も把握した上で融資の最終判断をしているか?
この中で「①業態」は重要なところです。書類だけでは詳しくわからない部分なので、申込の際には担当者に詳しく話してあげて下さい。
決算書の重要項目
最重要3項目
損益計算書(P/L)
その年度の経営成績を明らかにしています。売上高から当期純利益まで、各種費用を除きながら利益を算出します。
貸借対照表(B/S)
その年度の資産・負債、純資産を明らかにしています。通常直近3期分を比較して増減状況を見ます。
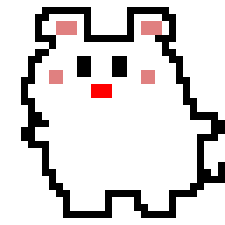
キャッシュフロー計算書
P/L、B/Sからはわからない会社の現金を生み出す力と利用方法を示したものです。中小企業には作成義務がないので、代わりに資金繰り表を作成している会社が多いです。
キャッシュフロー計算書と資金繰り表はほぼ同じ構造。
銀行では決算書を預かると、スコアリングと言って決算内容を機械判定にかけます。
そこで高い方からA、B、C、D・・・といったランク付けがされ、Aに行くほど融資が出しやすく、金利も低くなります。また、決算書の表面数字だけでは表せない部分などは、融資担当者が修正をかけてより正確なランクを出します。
決済権限者
融資の金額が大きくなればなるほど、スコアリングの悪い会社の申込であればあるほど、その銀行内で偉い人の決裁が必要になります。
支店長(支店によっても差があります)
⬇
本部(融資部長)
⬇
本部(役員)
決済権限者が偉い人になるほど、多くの手に渡っていくので融資判断に時間がかかります。
ちなみに担保を処分しても回収しきれない融資金額を信用貸と呼びますが、この信用貸の金額の大きさが決裁権限者が誰になるのかに大いに関係します。
メモ
融資金額-保全金額(担保や預金)=信用貸
借りやすいポイント
・業績が良好
・預金がある
・担保を出している
・保証協会付融資
①審査では業種平均とも比較されるので、同業他社より決算内容がいいとプラス材料です。
②銀行は預金者の大切なお金を融資するので、回収できるかどうかを慎重に見ています。そのため預金があること、担保があることはプラス材料です。もし返済できなくなっても、預金からの相殺や担保を差し押さえ、売却によって融資金の回収が図れるからです。そのため担保を処分して回収できる融資金額は借りやすいです。
③信用保証協会付融資は一種の担保になるので借りやすいです。銀行の立場からすると、債務者が返済できなくなった時に信用保証協会が代わりに融資金を返済(代位弁済)してくれるからです。債務者からすると、お金を返す先が銀行から信用保証協会に変わりますが、信用保証協会の取り立ては銀行以上にシビアになります。また、信用保証協会独自の審査と別途保証料が必要です。