
略してアパマンと呼ばれています。基本的に資産家、地主の方向けのローンです。
余談ですが私の先輩はアンパンマンと冗談を言っていました。
目次
アパート・マンションローンの融資事務の流れ
①資産家からの相談 或いは 業者持込
⬇ 必要書類の徴求、現地・資産調査
②審査1(全体を審査)
⬇ 協議・稟議申請
③審査2(つなぎ資金有【つなぎ資金無は⑤へ】)
⬇ 別途つなぎ資金稟議申請
④実行(つなぎ資金)
⬇ 必要書類の徴求、融資金の授受、担保設定
⑤実行(全体)
⬇ 必要書類の徴求、融資金の授受、担保設定
⑥管理
⬇ 融資先の状況の継続的な把握
⑦回収
融資先から融資金の回収を受ける
メモ
新規で収益物件を建てる場合、建築業者は着手金、中間金、完成時と複数に分けて請求するのが一般的です。つなぎ資金はこの着手金や中間金にあてるものです。
目的と資産背景
目的
収益物件投資の目的「相続対策」「土地有効活用」「生活費捻出」等の確認。明らかな生活費捻出のための場合は慎重に対応されます。収益物件は空室リスクなどのリスクがつきものであり、他の収入で生活費、更にそのリスクを補えることを前提でみられます。また、相続対策では高齢者の案件が多いため、事業継承者の調査についても十分に行われます。
資産背景
資産背景は主に預金と保有不動産の調査です。預金は他行含めた通帳残高を確認。
できるだけオープンにしたほうが審査にはプラス材料です
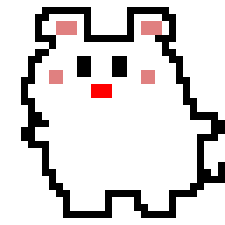
固定資産税名寄せ台帳や謄本などから保有不動産と付着権利を調べ、不動産の資産余力を把握します。不動産の評価額と担保としてとられているかどうかが大きく関わってきます。
不動産の評価が高い → 資産余力「大」
不動産の評価が低い → 資産余力「小」
付着権利無 → 資産余力「大」
付着権利有 → 資産余力「小」
今回計画している収益物件だけでは担保評価が足りない場合、添担保と言って、保有する他の不動産も担保をとる可能性があるので、資産余力は重要です。
返済能力
既存の返済能力
不動産所得+減価償却費+借入金利子-所得税-生活費 > 年間返済元利金
となっているか。
投資物件単体での返済能力
当該物件事業所得+減価償却費+借入金利子 > 金利上昇時年間返済元利金
となるか。※金利上昇時は3%程度を想定
投資物件の検証
借入利回り
借入利回り=年間収入÷借入金額×100
新築:8%、中古15%以上が望ましいです。
DSCR(デット・サービス・カバレッジ・レシオ)
(賃貸収入-減価償却を除く運営費用-設備投資額)÷返済元利金
元利金返済額を補えるだけのキャッシュフローを創出しているかを判断するための指標です。一般的にDSCR1.2未満は融資対象として回避するべきとされています。
物件単体の年間キャッシュフローで返済元利金を維持できるかどうか。
持ち出しとなる場合は総体で賄えるかどうか、自己資金により借入金額を減らせるか。
継続して返済ができるかどうかをみます。
金利
通常は複数金融機関で競合させると思います。
いくら借りられるかと、金利が何%になるかは、銀行によって変わりますので条件の良いところ、今後付き合っていきたい銀行を選んでいただければ大丈夫です。
金利については変動金利と3年・5年・10年固定金利などがありますが、一般的に固定期間が長くなるほど金利は高くなります。住宅ローンと違い変動金利だから低くなるとも限りません。また、アパマンは借入期間が長いので、○年固定金利を選ばれた場合は(何度か)固定期間終了時に金利の見直しとなります。
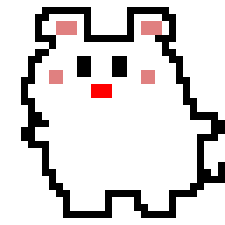
また、固定期間中の注意点として違約金がかかりますので、他の銀行に借り換える際はタイミングに気をつけて下さい。
まとめ
資産背景
・銀行に担保でとられていない、資産価値の高い不動産を多く持っているほど◎
・預金が多いほど◎
今回該当する収益物件
・個人の返済能力は余力があるか
・物件単体で年間の返済額が賄えるか(限界入居率も確認)
・優良な家賃保証は◎(例えばセキスイハイム不動産など大手はプラス材料)
銀行はリスクを嫌うので、
・今回該当する物件単体では担保評価が足りない
・立地上賃貸需要旺盛とは言えない物件
・自己資金がない
・返済能力と投資物件利回りが低い
等の場合は添担保を要求される可能性が高くなります。
あと申込人の家族構成、事業継承者についてもみられます。