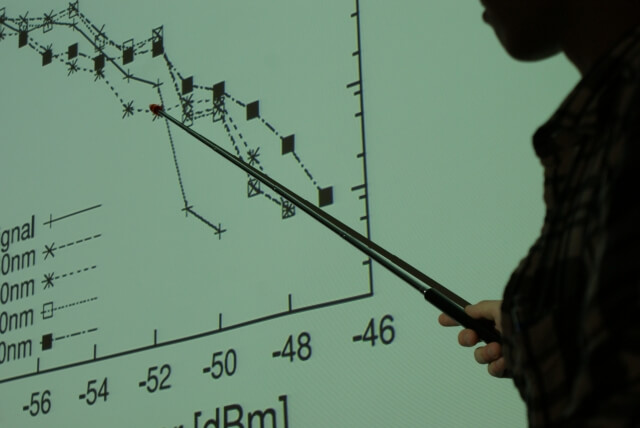
銀行員時代、融資案件の肝心なポイントとして学んだことです。
こういうところを見ているというご参考に。
①当座比率が急激に悪化
企業の支払原資の大半は当座資産(現預金・受取手形・売掛金)であり、反対に支払対象は1年以内に支払う債務である流動負債(支払手形、買掛金、短期借入金、未払法人税等)です。
当座比率の求め方
当座資産 ÷ 流動負債 × 100
上記計算式より当座比率は、企業の当面の支払能力を表す指標になります。
倒産企業は程度の差はあれ、当座比率の低下が兆候として事前に現れるので、当座資産に問題がなければ当座比率は高いほど良いです。問題がなければと言うのは、預金が銀行に拘束されていたり、不良売掛金、不良受取手形が含まれていた場合、実質的には支払原資とならないことから、それで仮に当座比率が高くても意味がありません。そのため実質的な支払能力を判断する必要があり、以下の点を分析します。
1.現預金勘定の拘束性
総合歩留率が30%に満たない場合は支払資金の枯渇状態とみなされます。倒産兆候と判断される恐れがあります。
総合歩留率の求め方
現預金 ÷ 長短借入金 × 100
2.売上債権対商品比率の推移分析(不良債権の見分け方1)
不良債権があるかどうかを知るためには、売上債権対商品比率の推移を調べると効果があります。売掛債権と商品との間に、通常は比例関係があります。もし、不良債権や粉飾があった場合、比例関係が崩れ、比率が異常に高くなることを手がかりに不良債権の有無を探ります。
売上債権対商品比率の求め方
売上債権 ÷ 商品(棚卸) × 100
メモ
売上債権 = 受取手形 + 売掛金 + 割引手形 + 裏書譲渡手形
3.売上債権回転期間の分析(不良債権の見分け方2)
売上債権の効率を売掛期間と受取手形決済期間の回転期間から推移を捉えて、不良債権の有無を探ります。
回転期間が短い = 債権回収が順調
回転期間が長い = 回収費用や貸倒損失の発生の危険が増え、財務の圧迫材料
となります。
売上債権回転期間(月)の求め方
売上債権 ÷ 売上高(平均月商)
メモ
売上債権 = 受取手形 + 売掛金 + 割引手形 + 裏書譲渡手形
4.売掛金の分析
連続2期の決算書の勘定科目別明細より、同一先に対して同金額の売掛金の計上は、まず不良債権と判断されます。また、半年以上前に発生している売掛金なども同様です。
| 2019年3月期決算書 | 2020年3月期決算書 |
| 売掛金 | 売掛金 |
| ○×商事 123,456円 | ○×商事 123,456円 |
| □△商店 100,234円 | □△商店 56,789円 |
| #%&販売 321,000円 | !!!商事 234,000円 |
上記の例では、○×商事の売掛金は2期連続で同額計上であり、不良資産とみます。
5.受取手形の分析
受取手形の中に、不渡手形と融通手形がないかを分析します。
① 不渡手形は、勘定科目明細から手形期日と銘柄を見ることで把握します。また、独立的な勘定科目で処理されている場合もあります。
② 融通手形の場合は、支払手形勘定に同一先に対する同一金額の計上を見ます。また、一定した期日以外の支払手形がある場合には、貸手形による融通手形操作を疑います。
②売上高に比べ売掛金が増加
通常、売掛金残高は売上の拡大に伴って増加します。しかし、売上増加と売掛金の増加が不釣合の場合、売掛債権回転期間を前期と比較して、回収条件の変更や新規販路拡大に伴う長期売掛がなければ、
① 大口の不良債権の発生
② 不良売掛金の増大
③ 粉飾決算
のいずれかに該当すると判断されます。
売掛金は棚卸資産とともに粉飾しやすい勘定科目です。粉飾計上で多いのは、
・架空の債権を計上
・決算月の押込販売と決算翌月の買戻
などです。
あと、通常の商取引において売掛金滞留期間は、長くても1ヶ月半程度と考えられるので、売掛金残高が売上高の60日以上ある場合は要注意と判断されたりします。
③売上高に比べ棚卸商品が増加
棚卸資産の回転月数(棚卸資産が平均月商に対して何ヶ月分あるか)を過去と比較して推移はどうなっているか、また同業他社と比べてどうかをみます。
例えば、従来より長期化していれば
・販売状況悪化による商品・製品の累増
・返品による不良在庫の滞留
・商品価格低下による出血販売回避のための在庫増の長期化
・供給先からの原料押込販売
などが考えられ、経営上好ましくない状態です。
④内容不明の貸付金が急増した
貸付金はお金を貸した時に使用する勘定科目です。中小零細企業では特に、会社と役員(社長等)との間でお金のやり取りがあることも多いです。
・会社が役員にお金を貸す→「役員貸付金」
・会社が役員からお金を借りる→「役員借入金」
役員報酬は期首から3ヶ月以内に決定しなければならないので、見通しが立たない中で役員報酬を決定するのはリスクがあります。そこで、役員貸付金を利用すれば期首から役員報酬を決める必要はないため、会社の業績をみながら役員の生活資金の確保ができます。しかしデメリットは「利息がかかること」と「銀行には不良債権とみられる」点です。
一例として、決算書に内容不明の貸付金(または仮払金)計上があるが、減収減益のため配当金、役員賞与はなしという決算報告を聞いたとします。
この場合で推測されるのは、中間決算時に役員賞与を貸付金(または仮払金)で支払ったところ、決算時に収益悪化により配当、役員賞与なしとなり、貸付金の精算が出来なくなったケースです。こういった場合不良債権とみなし、資産から不良勘定を除いて財務分析を行います。
⑤売上高や借入金に比べ支払利息の負担が多すぎる
損益計算書上の金利負担額が、総借入金に平均適用レートを乗じた金額より大きい場合、簿外借入や、支払手形の項目に借入金の一部を計上していないかなどを疑います。
問題がないケース
借入金の期中平均残高が高く、期末に決算対策で借入金を大幅返済した場合
問題があるケース
・資金繰り悪化により(取引銀行に伏せたまま)街金などで高利借入金を簿外処理した場合
・簿外による融通手形の発行で、支払金利のみ計上した場合
一般的に売上高に対して金利負担率が重すぎる場合は、売上規模に比べて借入金が多すぎることになります。
売上高対支払利息比率の求め方
( 支払利息 - 受取利息 ) ÷ 売上高 × 100
売上高対支払利息比率(金利負担能力)
2~3% 一般的
10%以上 要注意
取引先が高収益の会社でもない限り、10%に達しているということであれば、街金利用と判断されます。
まとめ
銀行のB/Sにおいて最も大きな資産は貸出金債権であり、P/Lにおける最大の柱は利息収入です。つまりお金を貸すのが仕事です。しかし、貸せればいいということではなく、健全な貸出資産を多く持つことが銀行の安定的な収益に繋がっています。そのため、融資には審査があり、今回はそのポイントとなるところを記事にしてみました。
どの場合でも言えるのは、
比較的大きな金額の動きがあったときは必ずその内容はチェックされます。